今回は、誰でも実践できる「勉強のコツ」についてのお話です。
ゲームを遊ぶとき、どうしていますか?
皆さんは、新しいゲームを始めるとき、どんなふうに遊びますか?
私は、チュートリアルを見ません。説明書も最初は読まないタイプです。
実はこれは、無意識ながら「学習の最短距離」=トライ&エラーの実践になっていたのです。
攻略本がなかった時代の遊び方
たとえば、私が子どものころはネットもまだ普及しておらず、攻略本も子どものお小遣いでは手に入りませんでした。
新しいゲームを買ってもらった日はワクワクが止まらず、説明書を開く前にとりあえずでプレイ開始。
飽きるまで遊んで、行き詰まったところでようやく説明書を読む。
すると「こんな操作もあるんだ!」と新しい発見に目を輝かせ、また遊びに戻る——。
これはまさに、トライ&エラーの作法そのものでした。
現代の丁寧すぎるチュートリアル
最近はチュートリアルが非常に親切なゲームが増えました。
一から十まで丁寧に説明してくれるのはありがたいのですが、私は少し苦手です。
ゲームの面白さは、最初に「手探り」で世界を探るワクワク感にあると思うのです。
なので、説明はあとでいい派です。
できればチュートリアルは別ページに分けて、本編はちょっと不親切なくらいがちょうどいいと思っています。
勉強もトライ&エラーで進めばいい
話がそれましたが、この「まず遊ぶ → 詰まる → 調べる → また遊ぶ」のサイクル、
実はそのまま勉強にも応用できるんです。
- まず知識を学ぶ
- 問題を解く
- 詰まったら調べる
- また問題を解く
ただそれだけの繰り返しが、学習の本質となります。
多くの学習サイトが「問題集 → 教科書確認 → 再チャレンジ」を推奨しているのも、
ゲームから学んだトライ&エラーが、勉強にも通用する証拠と言えるでしょう。
「ゲームは頭が悪くなる」は本当?
「ゲームは脳に悪い」「やりすぎるとバカになる」といった声もあります。
その理由の一つに「ゲームは無限にアドレナリンが出るように設計されていて、やめ時がわからなくなる」というものがあります。
しかし私は、これを勉強に活かすべき発明だと思っています。
Duolingoに見る“楽しい学び”の可能性
実際に、Duolingoのような外国語アプリは、
ゲームの仕組み(デイリー達成・ステージクリア・ランク制度など)を取り入れて、
「学びの継続」を促す工夫がされています。
こうした「遊びながら学べる」スタイルがもっと広まれば、勉強のハードルはかなり下がると思います。
ただ、課題もあります。
ゲームで遊ぶときまで学びたい人が少ない、継続的な収益を出すのが難しい、運営コストが高い……など、簡単ではありません。
今のゲームは“最適解”が早すぎる?
ゲームの遊び方自体も変わってきています。
各種配信サイト(youtubeなど)や企業サイトのおかげで、最適解が発売日から24時間以内に出るのが当たり前。
「手探り」より「効率」が優先される時代です。
でも、それに流されすぎると、本当に大切なトライ&エラーの経験が抜け落ちてしまうのではないでしょうか。
トライ&エラーは一生モノのスキル
確かに、トライ&エラーには時間がかかります。
非効率で、時代に合わないと思われるかもしれません。
けれどもこれは、人生においてどうしても避けられない作業なのです。
ゲームでなくても、熱中できる趣味がある人は、
「まずやってみる → 行き詰まる → 自分で考える」を繰り返してみてください。
それがあなたの学びの土台になっていくでしょう。
勉強ができなくても大丈夫
「勉強しなきゃ」と思っても、なかなか続かない。
そんな人にこそ、まずは「遊び」の中から学びの姿勢を見つけてほしいのです。
遊びをただの娯楽で終わらせず、「次につながるヒント」を見つけていく。それだけでも価値があります。
おわりに
トライ、そしてエラー。エラーを修正して、またトライ。
とても地道で、つまらないように見えるこの繰り返し。
私はゲームの中で、これを楽しく実践していました。
誰でも、今すぐ始められます。
すでに楽しいことがある人も、その向き合い方を少し変えるだけで、勉強に応用できるんです。
学ぶことから逃れられない人生。
それならば、できるだけ楽しく生きていきましょう!
今回も読んでくださってありがとうございました。また次回の記事でお会いしましょう。
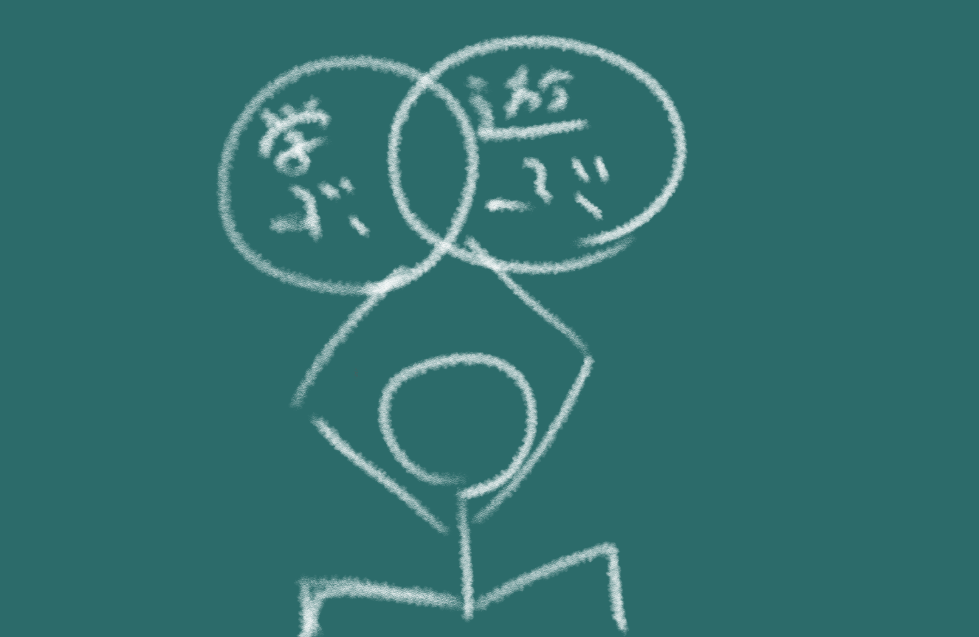
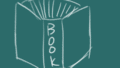
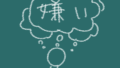
コメント