今回はプログラミングを学びたいと思っている人に向けたメッセージです。
どんな言語を学ぼうかな? いいですね。
まず作るアプリを決めなきゃ。 いいと思います。
よし、メモ帳に書くぞ! ちょっと待ってください。
違います。
これを入れてください
「VSCode プログラミングコードエディタ」
なにそれ?おいしいの?
youtubeでプログラミングの勉強したり、Progateやドットインストールも使ってるし、わざわざ英語を翻訳しながらMimoも使ってるけど聞いたことないな。今日のお昼までの私です。
こんなツール一回もおすすめされたことない! 私の素直な感想です。
このツールを使えばプログラミングにかかる大多数の手間を、ある程度減らせます。
使用する言語に応じた予測変換などもあり、<h1> と打つと </h1> が自動生成されます。めちゃくちゃ楽です。
なんで今までエディタの存在に気づかなかったんだ?誰か教えてくれても良かったんじゃないか?
独学の弊害だとわかっていつつも、私の心はそう叫びました。
なぜ私はプログラミングが楽になるツールにたどり着けなかったのか
結論から言えば前述した独学の弊害なのですが、私なりの事情もあります。
私のプログラミングの世界へ入った手順はこうです。
プログラミングをやりたい。ブログを運営するようになったし本格的に学びたい。そのためにいろんなサイトを見て回るぞ!と意気込んでネットサーフィンをしながらの数日間。
そのうちプログラムはメモ帳でも書けることを知り、そこから入っていきました。
それが大きな迷路への入口だということも知らずに。
「HTML、初心者」で検索して出てきたサイトには、使用するツールについて「メモ帳などのテキストエディタ」と軽く書いてあります。
この言葉の裏には
(操作が楽になる「エディタ」もあるけど初心者に説明するのはまだ早いし、慣れてる人は知ってるし、今深く説明する時間もない。それに自分のサイトで紹介するエディタを入れてもらえばお金も入るかもしれないから、今はとりあえず)メモ帳などのテキストエディタ
というふうに、私にとってはいちばん大事だった部分が、様々な都合によって省略されていたのです。
プログラミングを教える立場の方に伝えたいのですが
そもそも初心者には「エディタ」という専用ソフトを使う概念がない
のです。
<>の打ち込みがだるい、<p>とか覚えるのがだるい
なにか方法があるのかも?いやタイピングの速度を上げれば解決するのかな?と「寿司打」で高得点を狙う練習をする日々。
誰かに説明されなければ、決して出口にたどり着けない「無知」という迷宮は、深くて暗いのです。
プログラミングをするならエディタを導入しよう。
慣れてる人からすると当たり前かもしれませんが、そんな単純な発想すら初心者にはありません。
概念を知ると、世界がひらけます。
「VSCode」以外にもエディタが存在することをそこから知り始め、やっと自分に合ったプログラミングの環境を選べるようになりました。
エディタの導入が重要な理由は、野球に例えるとわかりやすいです。
野球をしたいと思った時にルールを覚えるところから入る人は少ないでしょう。
それと同じくらい、ボールを買ってボールのみでキャッチボールを始める人もいないはずです。
大体の人はまずボールとグローブ、追加予算があればバットを買って適当に遊んでみるでしょう。
素手でもボールを取れないことはないですが、素手では受ける面積が小さい上に、「手の痛み」という直接的な被害もあって危ないですよね。
プログラミングでエディタを使わないということは、野球のボールを素手で受け止めるのと同じこと
なのです。
野球について知っていれば、グローブの知識も大抵の人が持っているので、素手のほうが安く済んでもやらないでしょう。
ですがプログラミングについては、初心者にはまるで無知の領域が広がっており、エディタについての知識を得る機会がなく、また経験者にとっては様々な理由からあまり教えたがらないものなのです。
プログラミングを始める初心者で作るアプリや学ぶ言語が決まった人は、エディタを導入するところから入りましょう。特に、野球するならまずキャッチボールをしたり、バットを振りたいタイプの人にはおすすめです。私がそうであるから、という前提ですが。
悩んだら「VSCode プログラミングコードエディタ」
無料で拡張性も高いのでおすすめできると思います。
有識者の方がもしこのブログを見ていらしたら、より簡単で初心者向けなエディタも紹介していただけると、以前として独学のプログラミングという迷路をさまよう、私への一筋の光となることでしょう。
導入は非常に簡単なので割愛しますが、需要がありそうなら導入方法までお伝えしたいと思います。
エディタを活用して楽しく簡単にプログラミングを学ぼう。
今回も記事を読んでいただいてありがとうございました、また次回の記事でお会いしましょう。

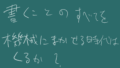
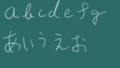
コメント