今回は「タルムード」の一説話のお話です。
「タルムード」とは?
全世界で数多くの成功を収めている民族、ユダヤ人。科学者アインシュタインから映画監督スピルバーグ、IT起業家のマーク・ザッカーバーグなどなど様々な分野で活躍しています。
そんなユダヤ人の聖典が「タルムード」です。彼らの成功哲学といわれています。
タルムードを知ることで少しでも彼らのような成功を収める秘訣を身に着けたい!そう思ったあなたにおすすめの記事です。
・注意点:厳密にはヘブライ語で書かれたもののみが聖典とみなされる(誤訳の可能性があるため)
本記事は、『ユダヤ人の成功哲学「タルムード」金言集』石角完爾 著を参考にして私なりの解釈を述べたものになります。ご了承ください。
さて今日のお話は・・・「金の冠をかぶった雀」です
ユダヤの最も有名な王、ソロモン王は賢者でもあり、鷲(ワシ)の背に乗って空を飛び、国内をくまなく見て回ったと言われます。
ある日、ソロモン王がいつものようにエルサレムから遠方の領国を目指して飛んでいた時、たまたま体調が悪くて、鷲から落ちそうになりました。
それを見ていた雀たちが何百羽と寄ってきて、ソロモン王が落ちないように支えました。
これに感謝したソロモン王は、雀たちに「お前たちに何でも欲しいものをあげよう」と言いました。
雀たちは巣に戻り、何をもらうか話し合いました。
- 「いつでも身を隠しておけるブドウ畑」
- 「いつでも水が飲める池」
- 「いつでも食べ物に困らないように野原に落穂(おちぼ)をまいてもらう」
様々な意見が出る中で、一羽の雀が言いました。
「ソロモン王と同じような金の冠をかぶって飛んだら、さぞかし誇らしく格好いいだろう」
雀たち全員がこれに賛成し、意見がまとまりました。
雀の代表がソロモン王のところに行き、「王様と同じ金の冠を全員にください。それが私たちの願いです」と申し出ました。
それを聞いたソロモン王は「それはあまり良い考えではないな。もう一度考え直してはどうだ」と助言しましたが、雀たちは、「ぜひ王冠をください」と繰り返して譲らなかった。「それほどいうなら仕方ない」とソロモン王は、雀たちの願いを叶えました。
金の冠をかぶった雀たちは、喜々として大空を飛び回りました。
すると、今まで雀を目にもくれなかった猟師たちが、金の冠をかぶっているために、全国で雀を狩るようになってしまいました。仲間たちはみんな撃ち殺され、イスラエルの雀は最後の五羽になってしまいました。
最後の五羽は命からがらソロモン王の所にかけつけ、「私たちが間違っていました。金の冠はもういりません」と言いました。
雀から金の冠が取りはずされ、少しずつ雀は平和を取り戻し、何年かのうちにまた元の数に戻ったということです。
この説話からわかること
ユダヤ人の母親は説話を子供にくり返し聞かせて、「あなたならどうする?」と尋ね、「それはなぜ?」とまた質問していったそうです。
この先に私なりの解釈と回答をのせますが、正解はありませんから、まずはご自身で考えてみてくださいね。
・・・さて、私が感じた重要な点は3点あります。
- 分不相応な要求は身を亡ぼす
- 他人の意見に根拠なく流されることのリスク
- 危険には早めに気付くのがいい
雀にとって金の冠は、どれだけ価値があっても雀の生活には不要なものです。実際、ブドウ畑や池など、実用的な要求も雀たちは考えていましたが、「ソロモン王のような」「格好いい」などと見栄や欲が混じった合理的でない選択に雀たちは流されてしまいました。
現代にあてはめて考えてみても、お金持ちになりたいという欲求から、根拠のない儲け話に流されて、結果的に財産を失う人がいると思います。「分不相応な要望を叶えようとする」ために、「他人の意見に流された」結果つらい目に合う、というわけです。
そう考えてみると、この説話のように家族や親族であっても他人の意見に流されて、合理的でない選択をするリスクに対する警告が込められていると思いました。
また冠を受け取ったあとも、最後の五羽になるまで冠を外さず、ソロモン王にお願いして外してもらっました。
猟師に狙われるようになった時点で脱ぎ捨てることもできたはずです。そうすれば、もっと早くに平穏が訪れ、雀の数が戻るまでの時間も短かったでしょう。
現代でも「損切り」という言葉があるように、失敗した時点でそれを認め、早くに撤退や改善をすることの大切さも同時に描かれていると感じました。
繰り返しになりますがこの説話の解釈に正解はありません。どうかご自身でも考えてみてください。
そして「こういう見方もできるかも」などコメントをくれるととても喜びます。
ここまで読んでくださってありがとうございました。また次回の記事でお会いしましょう!

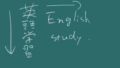
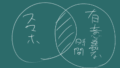
コメント