今回は、本を読みたいけど読めなくて困ってる人の助けになりたい、というお話です。
結論として知識は「食材」、本は「料理」、そしてそれらの情報を受け取る頭は「胃袋」だと考えてください。そして以下のStepを踏むことで、知識を本として美味しく楽しめるようになりましょう。
Step1.頭=「胃袋」
まずは頭から入ります。お腹が空かないと食欲がわかないように、頭の中に知識をいれるためにも、まずは頭を空っぽにする必要があります。
そのために必要なのが「アウトプットです」
アウトプットをしよう!と決めるだけでも効果があります。
これは私の体験なのですが、私は本からブログ記事の内容を思いつくことが多いです。ブログ記事を書こうと決めると、それだけで本が読みたくなるのです。
ブログをやっていなくても、SNSなどで「本を読んでみたい」とつぶやいてみたり、日記に「本を読もうと思っている」と書くだけで、食欲がわいてくるので、お試しください。
最近はネットを通すことで誰でもアウトプット可能な手段が増え、やりやすくなっていると思います。
Step2.知識=食材の選び方
アウトプットでお腹を空かせたら、食べたい食材、つまり欲しい知識を探します。
食べたい知識を見つけることと、頭の食欲をわかせることは逆でも良いのですが、それが可能な人は本記事の手順を考えるまでもなく本を手に取っていると思うので、一旦考えないものとします。
食材と知識には共通点があります。
それは、知識には鮮度があることです。
食材はとれたてが好ましく、料理になった後も作りたてが一番美味しいですよね。「知識」も同じです。「知識に対する自分の興味度合い」がそのまま「新鮮さ」に繋がるので、読書に不慣れな人はまず「読みたい本」を「興味深さ」で探しましょう。
たまに「自分の将来の役に立つ本を読まないといけない」や「なんでも読まないといけない」と思っている方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。
体に良いからと嫌いな野菜を食べ続ける食事制限は成功しないのと同じです。
だから自分の興味のある分野、ジャンルを優先して本を選びましょう。
できればスーパーに行く
「本を買うなら本屋にいけ」と言う人がいますが、それは自分の興味(=食材の鮮度)を見極めるためだ。と考えたら納得できるかと思います。
知識の鮮度は自分の興味度の高さで決まりますので、自分が食べたい「知識」を自分の目で探すことは理にかなっていると言えるでしょう。
Step3.本=「料理」の選び方
さて、いよいよ本を選ぶ段階になりました。
本は「料理」なので、当然「料理人」がいます。
それは作者です。
本の作者は念入りに調べましょう。
自分が欲しい作者がどこまでその食材の扱いに長けているのかで、本の美味しさも変わります。
それは料理の腕もピンキリで、文章の上手い下手があります。
これについては、私も人のことを言えたものではないのですが、やはり読みやすい文章を書く人の本は分かりやすいです。
難解な食材の味も調理法次第で美味しく最後まで食べられるのです。
読む側の感じ方も様々なので、何冊も似たような本が出ていたら、自分が読みやすいと思うものを買ってください。
小説を選んだけど、漫画版が出ていたからそっちが読みやすいからそっちにする、でも全然構いません。
スーパーの試食品を食べる感覚で、本の内容を数ページ見てみるのも有効です。
ネットで出てくるあらすじは、書き手が著者以外の可能性があるので、読む本を決める時にはおすすめしません。可能であればAmazonのサンプルページが良いでしょう。
私が言うのもなんですが、ブログやyoutubeのまとめ動画などは、食材選び=興味のある知識を探すとっかかり程度に利用するのが良いと思います。
こうして手に入れた本は、頭の準備も万端で、良い食材が選べていて、料理人の腕前も期待できるので、完食しやすくなります。
たまには途中のStepで躓くこともある
美味しそうだと思った料理の味付けが微妙だった、食材が実は消費期限切れだった、食べてるうちに満腹になってしまった、などあると思います。
そんな時には、冷静に「どこのStepが失敗だったか」を自分の中で考えてみてください。
- 次はもっとアウトプットして頭を空かせてみよう
- 自分が手に入れたい知識にもっと素直に従ってみよう
- 別の作者を選ぼう
などなど。すると、対策が立てやすくなります。
だんだん、「本が読めなかった」という失敗を防げるようになってくるのです。
まとめ
知識は「食材」、本は「料理」、そしてそれらの情報を受け取る頭は「胃袋」です。
胃袋を空にして(アウトプット)、食材を選び、料理を選ぶ。
料理と同じように、感じ方に個人差があると自覚し、自分にとっての「読みやすい本」を見つけていきましょう。
もし美味しい料理や食材に出会えたら、同じ作者の別の本を読んだり、近しいジャンルの知識を探したりと応用も効きます。
美味しい料理をもっと食べたいと思うように、美味しい本も読めば読むほど「もっと読みたい!」となっていきます。
食事と同じくらい、読書を楽しめる人が増えるように祈っています。
今回も読んでくださってありがとうございました。また次回の記事でお会いしましょう。
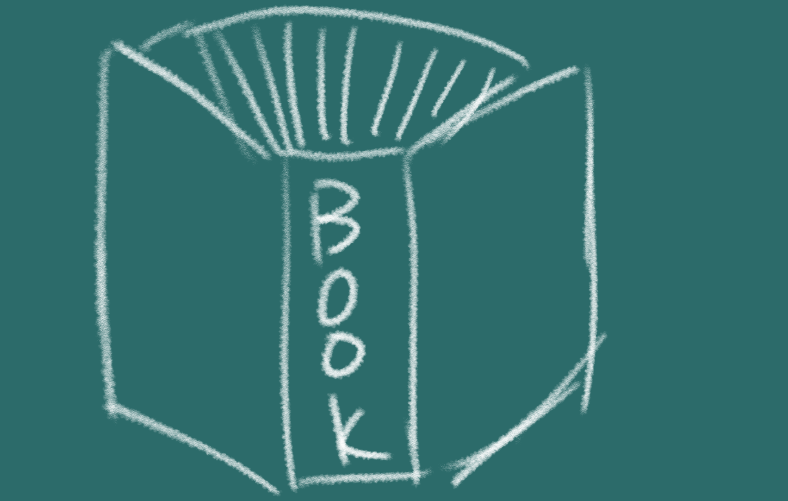
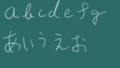
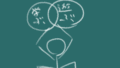
コメント